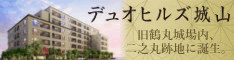もっと鹿児島が知りたい[4]薩摩切子の話

切子(きりこ)ガラスの切子とは「カット・削る」の意味で、ガラスの表面を削り取り、光の屈折や反射が美しい模様を生み出します。薩摩切子は鹿児島に150年前に誕生したガラス工芸品で、透明ガラスに色ガラスを被せて模様を削り込んだもので、美しい輝きと色を生み出しています。
日本のガラスの歴史
古墳時代の日本では、ガラスは高貴な身分の人々の装飾品として用いられ、遺跡の発掘では美しいガラス玉が見つかっています。
奈良時代になって遣唐使が派遣されるなど大陸との交流が始まると外国のガラス器ももたらされ、正倉院には「紺瑠璃杯」や「白瑠璃碗」等が残されています。奈良時代、我が国でもガラス工芸技術は隆盛となりましたが、鎌倉時代には衰退してしまいました。
戦国時代末期・江戸時代初期に西洋のガラスが輸入され、古く「瑠璃」と呼ばれていたガラスは、「びいどろ」、「ぎやまん」などと呼ばれるようになりました。「びいどろ」はポルトガル語に由来した普通の吹きガラスのことをいい、「ぎやまん」はオランダ語のダイヤモンドに由来した言葉で、江戸時代の後期にはカットされたガラス器を指すようになりました。このカットガラスが「江戸切子」と呼ばれるものです。
江戸時代はガラス製法が大きく発展した時代でした。鉛と硝石を原料にした鉛ガラスを鋳型に流し込んで外形をこしらえ、次ぎに内側を削り出して器にするという製法から、長い管の先に溶けたガラスを絡め、形を整えながら息を吹き込んで中空の器を作る吹き竿を使った製法が輸入され、ガラスは工芸品としての完成度を高めていきました。そして、無色のガラスに多くのカット面を加えて光の乱反射の美しさを楽しむ「江戸切子」が誕生しました
薩摩ガラスの歴史
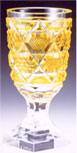 薩摩では、弘化3年(1846年)、島津家第27代・藩主島津斉興によって中村騎射場跡に製薬館・医薬館が創設され、そこでの実験や薬品保存に用いるための医薬用ガラス器の製造が始められたのが薩摩ガラス誕生となりました。江戸の「加賀屋」からガラス職人・四本亀次郎が招かれ製薬館近くに「硝子製造竈(かま)」が作られてガラスの本格的製造が始まりました。
薩摩では、弘化3年(1846年)、島津家第27代・藩主島津斉興によって中村騎射場跡に製薬館・医薬館が創設され、そこでの実験や薬品保存に用いるための医薬用ガラス器の製造が始められたのが薩摩ガラス誕生となりました。江戸の「加賀屋」からガラス職人・四本亀次郎が招かれ製薬館近くに「硝子製造竈(かま)」が作られてガラスの本格的製造が始まりました。
嘉永4年(1851年)に藩主となった島津家第28代島津斉彬は、城内の花園跡精錬所で宇宿(うすき)彦右衛門・市木正右衛門・中原猶介らに着色ガラスの研究をさせました。彼等は苦心の末に、銅粉で暗赤色、金粉で明赤色を発する紅色ガラスの製造に成功しました。
安政2年(1855年)、斉彬は西欧風の産業国家の建設を目指して、鹿児島市郊外の磯の地に西洋技術を取り入れた工場群から成る大工業地帯「集成館事業」の経営を始めました。ここに「硝子方」(工場)が設営されて、紅色の他に藍・紫・緑などの発色にも成功し、特に紅ガラスは、当時、薩摩藩でしか発色できず、「薩摩の紅ガラス」として藩内外で珍重されました。 透明度の高いクリスタルガラスや板ガラスの製造にも成功し、薩摩切子の生産が始まると、薩摩ビードロの名で愛好されました。
安政5年(1858年)、オランダの医師ポンぺは集成館のガラス工場を訪れ、「100人を超える職人が働いていて、日常品から奢侈品まであらゆる種類のガラス製品を見ることができた」とその活動の盛んなこと、技術の高さ、作品の素晴らしさについて記しています。
安政5年(1858年)7月、斉彬は家督を継いでわずか7年で急死します。斉彬の死後、安政2年から始まった西洋技術による藩の産業振興を目指した「集成館事業」も、その莫大な投資が薩摩藩の財政を圧迫しているとの理由で、ほとんどが縮小・閉鎖されることになりました。
さらに、文久3年(1863年)7月、生麦事件に端を発した薩英戦争で集成館の工場群は英国艦から砲撃を受け、多くが破壊焼失してガラス工場も壊滅してしまいました。この戦争で西洋技術の圧倒的優越を思い知らされた島津家第29代・藩主島津忠義は「集成館事業」の再興を命じ、同年10月、工場再建が始まりました。この時、ガラス工場も再建されたかどうかは不明です。
慶応2年(1866年)1月には英国外交官アーネスト・サトウが、6月に英国公使パークスが磯にある藩主の庭園にほど近いガラス工場を訪れ、薩摩切子の技術・芸術性の高さを褒め称えています。また、明治2年に斉彬の五女・寧姫(やすひめ)が磯訪問土産にガラス器を持ちかえったという記録もあり、この頃まで薩摩ガラスの製造は続いていたのではないかと思われます。しかし、明治10年(1877年)の西南戦争で、世界に誇れるほどの薩摩切子の技術・伝統は完全に消滅してしまいました。
薩摩切子の特徴・伝統の技復活
 薩摩切子の特徴は、透明なガラスに色ガラスを被せて溶着させた後、格子状に溝を入れる独特の製法よって生じる有色から無色へのグラデーション「ぼかし」の美しさにあります。
薩摩切子の特徴は、透明なガラスに色ガラスを被せて溶着させた後、格子状に溝を入れる独特の製法よって生じる有色から無色へのグラデーション「ぼかし」の美しさにあります。
薩摩切子は見る角度によって、色被せガラスと透明ガラスを通った光が複雑に屈折して交錯し、カット面で乱反射した光が加わって、趣の異なった華麗な光の芸術を織り成します。 当時、ガラスのカットは、回転させた円盤状の砥石に作品を押し当てて線を刻んだのですが、太い線も細い線も同じ砥石を使用したらしく、イギリスやチェコ(ボヘミア)などの西洋ガラスに比して細い線が鋭い切り込みになっていないのも特徴の一つになっています。
美しい「ぼかし」を生み出すためには色ガラスを被せた厚みが均一でなくてはなりませんし、カットについても同様で、薩摩切子の技術の高さがうかがえます。
 今日残された薩摩切子は足付きの杯(ワイングラス・リキュールグラス)や酒瓶(フラスコ)・足付きの鉢などの西洋風作品と、盃・段重・急須・碗などの和風作品とに大別されます。色は紅・藍が主流で、模様は六角・八角の籠目が多く残されています。島津斉彬は薩摩切子を諸大名への贈り物などにしていましたが、安政5年(1858年)の斉彬の死後ガラス工場は閉鎖され、薩英戦争で設備は破壊され、西南戦争でその製法技術は途絶えてしまい、長い間、薩摩切子の製法は謎とされてきました。 昭和58年(1963年)、薩摩切子再興が図られ、昭和60年に薩摩ガラス工芸(㈱)社が創立されて、本格的な活動が始まりました。昭和61年には紅・藍・紫・緑の4色のガラス器が復元され、昭和63年には金赤色が、平成元年には黄色が復元され、今日、薩摩切子の全6色が復元されています。
今日残された薩摩切子は足付きの杯(ワイングラス・リキュールグラス)や酒瓶(フラスコ)・足付きの鉢などの西洋風作品と、盃・段重・急須・碗などの和風作品とに大別されます。色は紅・藍が主流で、模様は六角・八角の籠目が多く残されています。島津斉彬は薩摩切子を諸大名への贈り物などにしていましたが、安政5年(1858年)の斉彬の死後ガラス工場は閉鎖され、薩英戦争で設備は破壊され、西南戦争でその製法技術は途絶えてしまい、長い間、薩摩切子の製法は謎とされてきました。 昭和58年(1963年)、薩摩切子再興が図られ、昭和60年に薩摩ガラス工芸(㈱)社が創立されて、本格的な活動が始まりました。昭和61年には紅・藍・紫・緑の4色のガラス器が復元され、昭和63年には金赤色が、平成元年には黄色が復元され、今日、薩摩切子の全6色が復元されています。
 ホームへ戻る
ホームへ戻る 詳細および申し込みはコチラ(PDF)
詳細および申し込みはコチラ(PDF)